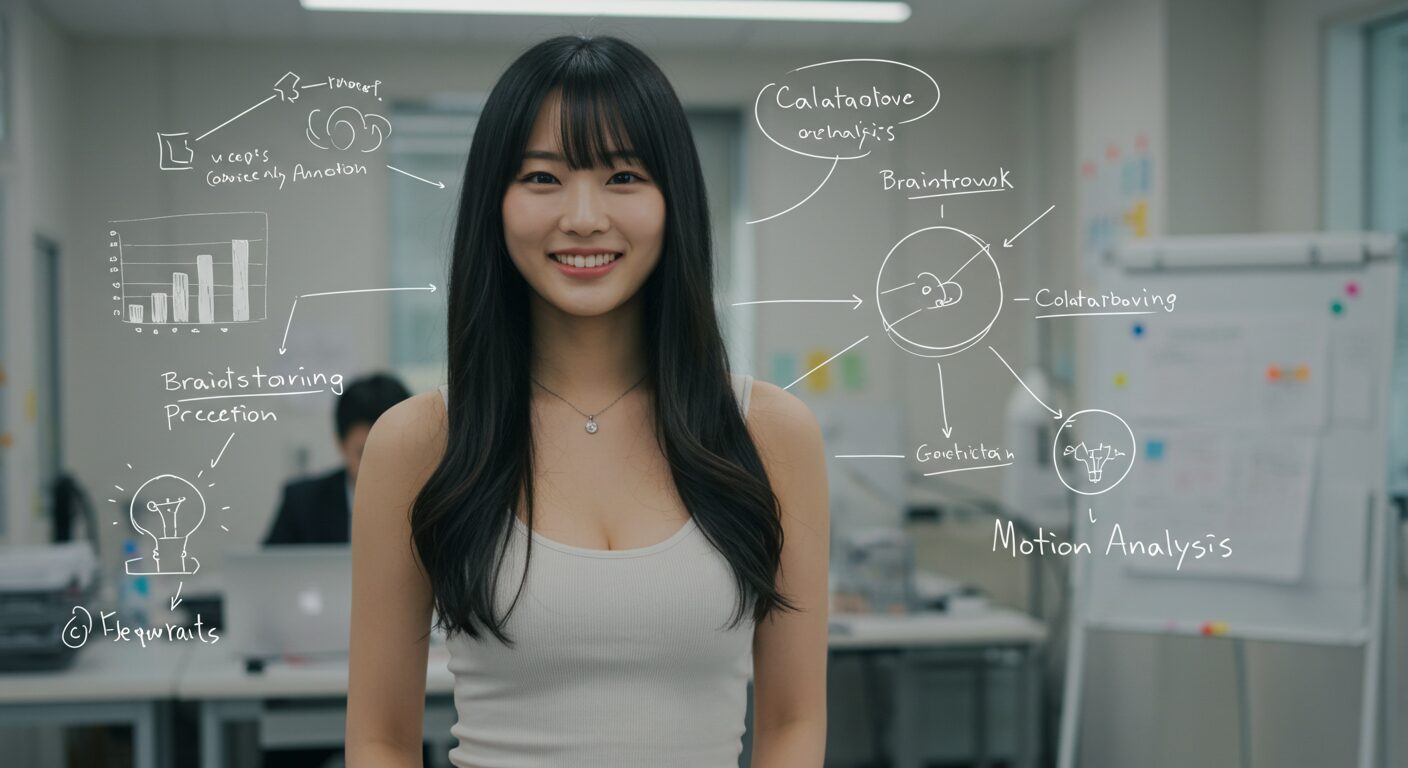問題
Ⅲ-6 サーブリッグ分析に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 「つかむ」は第1類の基本動作に含まれる。
② 第2類の基本動作は、第1類の基本動作を促進する動作である。
③ 改善の着眼点として、サーブリッグ分析では動作を3種類に大別している。
④ 第3類の基本動作は、作業を行わない動作要素である。
⑤ 「探す」は第2類の基本動作に含まれる。
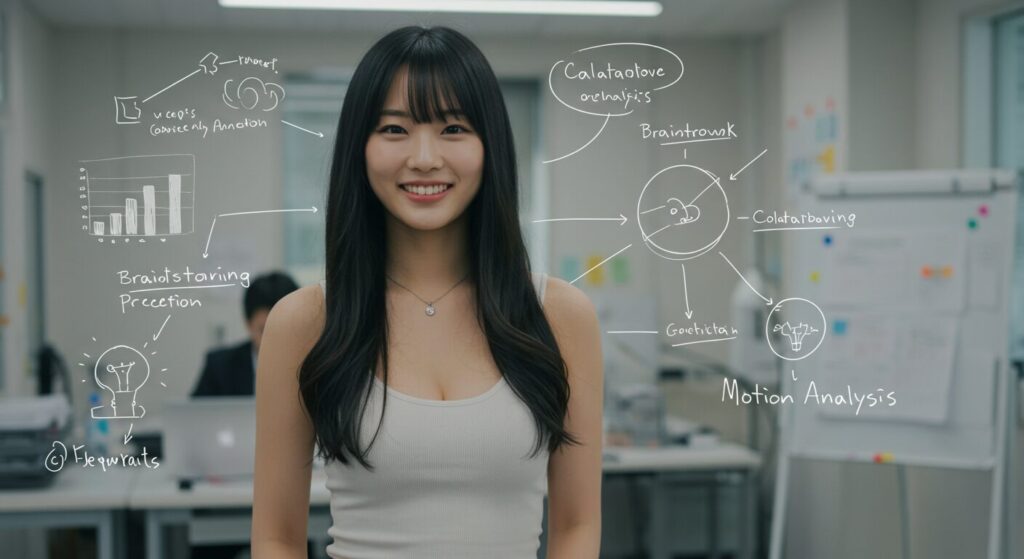
解答
正解は 2 になります。
サーブリッグ分析の概要
サーブリッグ分析は、作業を細かい動作要素に分解し、無駄を見つけて作業効率を高めるための分析手法です。
F.B.ギルブレスによって提唱され、18種類の基本動作(動素)に分類されます。
これらの動作は有用度に応じて「第1類」「第2類」「第3類」の3つに分けられます。
- 第1類:仕事遂行に必要な動作(例:つかむ、運ぶ、組み立てるなど)
- 第2類:第1類を補助するが、できれば排除したい動作(例:探す、選ぶ、考えるなど)
- 第3類:作業を行わない、完全に排除すべき動作(例:保持、遅れ、休むなど)
各選択肢の詳細解説
①「つかむ」は第1類の基本動作に含まれる。
これは正しい記述です。
「つかむ(Grasp)」は第1類に分類され、作業遂行に不可欠な動作とされています。
第1類には他に「空手移動」「運ぶ」「位置決め」「組み合せる」「分解する」「使う」「手放す」「調べる」などがあります。
②第2類の基本動作は、第1類の基本動作を促進する動作である。
この記述は不適切です。
第2類の基本動作は、第1類の動作を促進するものではなく、むしろ第1類の動作を遅らせる性質を持っています。
第2類は「探す」「選ぶ」「考える」「見出す」「用意する」などで、できるだけ排除・削減すべき動作です。
第1類の作業をスムーズにするためのものではありません。
③改善の着眼点として、サーブリッグ分析では動作を3種類に大別している。
この記述は正しいです。
サーブリッグ分析では、動作を有用度で「第1類」「第2類」「第3類」の3種類に大別します。
それぞれの動作グループごとに改善の優先順位や着眼点が異なります。
④第3類の基本動作は、作業を行わない動作要素である。
この記述は正しいです。
第3類は「保持(つかみ続ける)」「避けられない遅れ」「避けられる遅れ」「休む」など、
作業をしていない状態やムダな動作であり、完全に排除すべきものです。
⑤「探す」は第2類の基本動作に含まれる。
この記述は正しいです。
「探す(Search)」は第2類に分類され、作業効率を下げる要素のため、できるだけ削減すべき動作とされています。
まとめ:問題の要点
- サーブリッグ分析は作業を18の基本動作に分解し、3つのグループ(第1類・第2類・第3類)に分類する。
- 第2類の動作は第1類を促進するものではなく、むしろ遅らせる性質を持つため、排除・削減の対象となる。
- 今回の問題では「第2類の基本動作は、第1類の基本動作を促進する動作である」という記述が最も不適切である。
感想
サーブリッグ分析、お久しぶりなイメージですが過去問でもたくさん出てきます。
詳細はこの時に書いています。

が。今日は不正解。
ちょっと引っかかっちゃいました。
あらためてこの過去問見て学習せねば。
過去問、体裁とか変だったので最近の書き方へと大幅に修正かけました。
このページはしょっちゅう見るもんなあ。