問題
Ⅲ-18 直交配列表を用いた実験計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 2水準系の直交配列表には、L8、L16、L32などがある。
② 8つの因子とその交互作用をすべて分析するとき、L8の直交配列表を用いるのが適切である。
③ 2水準系直交配列表に、3水準因子を割り付けることもできる。
④ 交互作用がある場合は、線点図を利用し交互作用の現れる列を把握する必要がある。
⑤ L27は、3水準系の直交配列表である。

解答
正解は 2 になります。
問題の背景と全体像
直交配列表は、実験計画法において複数の因子(要因)を効率的に配置し、最小の実験回数で信頼性の高い結果を得るためのツールです。
各選択肢が直交配列表の特性や使用方法と整合しているかを検証し、不適切な記述を特定します。
各選択肢の徹底検証
① 「2水準系の直交配列表には、L8、L16、L32などがある」
- 適切性: 適切
- 解説:
2水準系の直交配列表は、各因子が2つの水準(例:高温/低温、圧力あり/なし)を持つ実験に使用されます。- L8: 7因子を8回の実験で評価可能
- L16: 15因子を16回の実験で評価可能
- L32: 31因子を32回の実験で評価可能
これらは製造業や化学実験で頻繁に活用されます。
→ 定義が正確→適切
② 「8つの因子とその交互作用をすべて分析するとき、L8の直交配列表を用いるのが適切である」
- 不適切性: 不適切
- 誤りの核心:
L8直交表は7列しかありません。8つの主効果(各因子単独の影響)を割り付けるだけでも不足します。
さらに、すべての2因子間の交互作用(例:因子A×因子B、因子A×因子C)を分析するには、28通りの組み合わせが必要です。L8ではこれに対応できません。- 具体例:自動車部品の材質(A)、加工温度(B)、圧力(C)の3因子の場合、A×B、A×C、B×Cの交互作用分析が必要ですが、L8では列数が不足します。
→ 列数不足のため不適切
③ 「2水準系直交配列表に、3水準因子を割り付けることもできる」
- 適切性: 適切
- 解説:
擬似水準法を用いれば、2水準系直交表に3水準因子を割り付けられます。- 具体例:2水準のL8直交表の2列を組み合わせ、以下のように3水準を表現:
| 列1 | 列2 | 3水準 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 水準1 |
| 1 | 2 | 水準2 |
| 2 | 1 | 水準3 |
→ 手法が存在→適切
④ 「交互作用がある場合は、線点図を利用し交互作用の現れる列を把握する必要がある」
- 適切性: 適切
- 解説:
線点図は、特定の列に現れる交互作用を視覚的に示します。- 具体例:L8直交表では、因子A(列1)と因子B(列2)の交互作用が列3に現れることが線点図で明示されます。
→ 標準的な手法→適切
⑤ 「L27は、3水準系の直交配列表である」
- 適切性: 適切
- 解説:
L27直交表は3水準の因子を最大13個まで扱えます。- 具体例:化学反応の温度(3水準)、触媒量(3水準)、反応時間(3水準)を同時に評価する場合に活用されます。
→ 正しい定義→適切
まとめ:技術士試験の重要ポイント
正解:②
誤りの核心
L8直交表は7列しか持たないため、8つの主効果を配置することすら不可能です。さらに、すべての交互作用を分析するには列数が圧倒的に不足します。
具体的には、L16やL32などの直交配列表が適切です。これらの直交配列表は以下の特徴を持ちます:
- L16: 15列あり、最大15因子まで割り付け可能
- L32: 31列あり、最大31因子まで割り付け可能
8つの因子とそのすべての交互作用を分析するには、少なくともL32を使用する必要があります。
L32であれば、8つの主効果と多くの交互作用を割り付けるのに十分な列数があります。
ただし、すべての交互作用を完全に分析するには、さらに大きな直交配列表が必要になる可能性があります。
実際の実験では、重要と思われる交互作用のみを選択して分析することが一般的です。
直交配列表の基本特性
| 直交表 | 水準数 | 最大因子数 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| L8 | 2 | 7 | 小規模実験向け |
| L27 | 3 | 13 | 複雑な3水準実験に対応 |
感想
うわ、直交配列表出てきちゃったよ・・・。
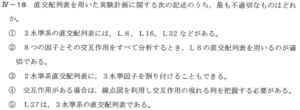
過去記事ではチンプンカンプンだから試験に出てきたら捨てるけど、次出たら学ぼう、なんて書いたんですよね。
解説文書いててもピンとこないんだよなあ。
先延ばししようかな・・・・。









