問題
Ⅲ-14 定量発注方式に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 定量発注方式の発注点は、安全在庫量によって決められる。
② 定量発注方式は、ABC分析の後、BランクとCランクの製品に用いられる。
③ 発注量は、一般的に経済的発注量を用いる。
④ 定量発注方式の簡易版がダブルビン法である。
⑤ 定量発注方式と発注点方式は同じものである。

解答
正解は 1 になります。
定量発注方式の概要
定量発注方式は、在庫管理の代表的な手法で、一定の在庫数量を下回ったタイミングで、あらかじめ決めた発注量だけ商品や部品を補充する方式です。
主に需要が安定している品目に適用され、「必要なときに、必要な分だけ」を実現するための効率的な管理法とされています。
- 発注点…在庫がこの点に達したら発注
- 発注量…毎回決まった一定量で補充
- 在庫切れ回避やコスト最適化のために活用
実際の現場では、数値管理や運用ツール(ダブルビン法など)も使いながら、欠品や過剰在庫を抑える工夫が重要となります。
各選択肢の詳細解説
① 定量発注方式の発注点は、安全在庫量によって決められる。
これは不適切な記述です。
発注点の設定に「安全在庫量」は関わりますが、発注点=安全在庫量 ではありません。
発注点は【調達リードタイム中に消費する量(=平均使用量×リードタイム)+安全在庫量】で求めます。
安全在庫だけを基準にしてしまうと、実際に必要な補充量や発注タイミングを正しく管理できず、在庫切れや余剰リスクが高まります。
発注点の公式
発注点 = 調達リードタイム中の平均使用量 + 安全在庫量
安全在庫はあくまで予期しない変動や遅延に備えるための「クッション」であり、発注点そのものではありません。
② 定量発注方式は、ABC分析の後、BランクとCランクの製品に用いられる。
この記述は正しいです。
ABC分析は、多数の品目を重要度や取扱量に応じてA・B・Cに分類する方法です。最重要のAランク品は発注頻度や数量の最適化がより厳密に求められるため、より細かな管理手法(たとえば定期発注方式)が採用されます。
一方、B・Cランク品は管理コストや手間を減らすために、定量発注方式(決まった発注点と数量による自動管理)がよく活用されます。
③ 発注量は、一般的に経済的発注量を用いる。
この選択肢も正しいです。
経済的発注量(EOQ:Economic Order Quantity)は、「発注コスト」と「在庫保管コスト」が最も小さくなる最適な発注量です。
定量発注方式では、その都度このEOQを使うことでトータルコストを削減し、運用の標準化・自動化を図ります。
EOQの基本式
$$EOQ = \sqrt{2DS/H}$$
D=年間需要量、S=1回当たりの発注コスト、H=1単位当たり年間在庫コスト
④ 定量発注方式の簡易版がダブルビン法である。
この記述は正しいです。
ダブルビン法(Two-Bin system)は、補充用の在庫を2つの容器(ビン)で管理し、ひとつが空になった段階で補充発注する仕組みです。
現場作業者でも運用しやすい「定量発注方式の簡易版」として幅広く利用されています。
特に頻繁な補充が不要な低価格部品などに適しています。
⑤ 定量発注方式と発注点方式は同じものである。
こちらも正しい記述です。
定量発注方式は、英語で「Reorder Point System」=発注点方式とも呼ばれます。
どちらも「発注点に到達したら毎回同じ量を発注する」という仕組みのため、実務上は同じ意味として扱われます。
まとめ
- 定量発注方式は、発注点・経済的発注量(EOQ)・安全在庫などで在庫補充を効率化する基本手法
- 発注点の設定は「リードタイム中の需要+安全在庫量」が原則であり、安全在庫だけで決まるわけではない
- ダブルビン法は定量発注方式の使いやすい簡易版として現場で普及
- ABC分析によるB・Cランク品管理にも多く活用される
- 定量発注方式=発注点方式と呼称されることも多い
感想
類似の問題はありますが、そのものズバリ!というのではないですね。
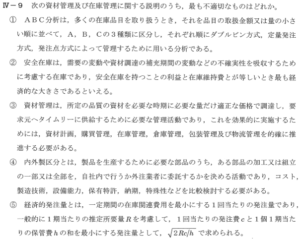


発注方式、設計屋であるワタクシにはあまりなじみがなく。
全部購買さんにお任せしておりました。
なるほどねえ、こんな世界もあるんだよなあ。
経営工学のお勉強を始めて、何度かはきいたことあるので以前よりマシ、というレベルですね。
今日は残念ながら不正解。
まだまだ勉強が足りませんね。









