問題
Ⅲ-1 IE手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 標準時間資料法は、標準時間を設定するための間接測定法であるから、作業内容に応じたレイティングを行う必要がある。
② ストップウォッチ法における早戻法は、要素作業の終了ごとに時計を止めて時間を読み、すぐに時計を0に戻して次の要素作業時間の測定を開始する方法である。
③ ワークサンプリング法における観測の目的には、一連の作業に対して、現状の余裕率を把握し、適切な余裕率を設定する場合が含まれる。
④ サーブリッグ分析は、人間が行う作業動作を改善するために、あらゆる作業に共通すると考えられる基本動作を18に分類し、それぞれに名称と記号を与えた手法である。
⑤ 作業者工程分析の対象は人であり、作業者の行動を系統的に記述するもので、材料、部品、仕掛品、製品などの物を分析の対象としてはならない。

解答
正解は 1 になります。
問題の概要
この問題では、IE(インダストリアル・エンジニアリング)手法に関する複数の記述の中から、「最も不適切なもの」を選ぶことが求められています。
IE手法とは、生産性向上や作業の効率化・標準化を目的とした分析・評価・改善技法の総称で、多くの業界で活用されています。
IE手法には様々な種類があり、例えばストップウォッチ法やワークサンプリング法、サーブリッグ分析、作業者工程分析などがあります。
これらの手法の基本的な考え方や誤りやすいポイントを押さえることが、技術士試験だけでなく実際の現場改善・管理にも大いに役立ちます。
各選択肢の詳細解説
① 標準時間資料法は、標準時間を設定するための間接測定法であるから、作業内容に応じたレイティングを行う必要がある。
解説:
- 標準時間資料法(PMTS/PTS法)とは、実際の作業を観測することなく、既に体系化された標準時間データを用いて標準時間を決定する方法です。
- この手法は、作業の細分化(たとえば「物をとる」「移動する」など)ごとに、あらかじめ決まった標準値(表)から合計して作業全体の時間を見積もる間接法です。
- 「レイティング」は観測者が作業の速さ・遅さ(能力レベル)を評価・補正する操作ですが、標準時間資料法では「観測」自体をしないため、レイティングの必要はありません。
- よって、記述の「レイティングが必要」という箇所が誤りとなります。
② ストップウォッチ法における早戻法は、要素作業の終了ごとに時計を止めて時間を読み、すぐに時計を0に戻して次の要素作業時間の測定を開始する方法である。
解説:
- ストップウォッチ法は、実際の作業を観測しストップウォッチで時間計測する直接計測法です。
- 早戻法(フライバック法とも言う)は、要素作業ごとにストップウォッチをゼロに戻し(リセット)、次の測定へ即座に移る方式です。
- 記述の通り、作業ごとに時計を止めて測定→ゼロ戻し→次作業、という手順。この説明は正しいです。
③ ワークサンプリング法における観測の目的には、一連の作業に対して、現状の余裕率を把握し、適切な余裕率を設定する場合が含まれる。
解説:
- ワークサンプリング法は、作業や活動の状態をランダムまたは一定間隔でサンプリング観測し、その状態(たとえば「作業中」「待機中」「手持ち」など)の発生比率を統計的に調べる手法です。
- この法では、「余裕率」(例:手待ちや休憩の割合)なども調査・把握できます。
- よって、「現状の余裕率を把握し、適切な余裕率を設定する」目的は含まれます。記述は正しいです。
④ サーブリッグ分析は、人間が行う作業動作を改善するために、あらゆる作業に共通すると考えられる基本動作を18に分類し、それぞれに名称と記号を与えた手法である。
解説:
- サーブリッグ分析(サーブリッグ図・サーブリッグ法)は、作業の動作や動線を要素ごと(拾い上げる・持ち運ぶ・置く、など)に分解し、分析するIE手法のひとつです。
- この分析では、人間の作業動作を18種類のサーブリッグ動作(Therblig)に分類し、名称/記号を設定しています。
- 例:とる(Grasp)、運ぶ(Transport loaded)、探す(Search)など。
- よって、この記述も正しいです。
⑤ 作業者工程分析の対象は人であり、作業者の行動を系統的に記述するもので、材料、部品、仕掛品、製品などの物を分析の対象としてはならない。
解説:
- 作業者工程分析は、作業者(人)の一連の動きを工程として図や記号を使って表すIE手法です。
- 対象は基本的に「人」ですが、実際には物(材料、部品等)を排除するものではなく、物の流れも分析の対象となる場合があります。
- ただし本選択肢の前半は「作業者に着目する分析」である旨がある程度正しいため、「物“だけ”を対象にする分析ではない」と考えれば大きな誤りとは言えません。
- 文末の「物を分析の対象としてはならない」という断定は強すぎるものの、完全な誤りであるとは一般的には扱われません。
まとめ・要点
- IE手法(インダストリアル・エンジニアリング手法)は、現場改善や生産管理における重要な技法群で、標準時間設定や工程分析など幅広く応用されています。
- 各手法の「定義」と「使い方の特徴」「間違えやすいポイント」を正しく理解することは、技術士試験対策・実務どちらにも有用です。
- 標準時間資料法では「レイティング」は不要である点が鍵となり、この知識が今回の正解の根拠として極めて重要です。
- ワークサンプリング法・ストップウォッチ法・サーブリッグ分析の定義や特徴も頻出事項なので、しっかり押さえておきましょう。
感想
令和元年は年功が変わったということで再試験が行われています。
これはシステム的に仕方がないのでしょうけれども。
令和元年の試験問題、回答的にちょっと微妙なのがあったから再試験か、なんて勘違いしてしまいましたよ!
さて、令和元年度(再)ですが。見た感じ、令和元年度の試験よりも難しい気がします。
似たようなのはないですし。
しっかりと作られていますね。さそが最高レベルの試験。
さて、本日の問題。
無事正解しました。
IEって結構出ますもんね。
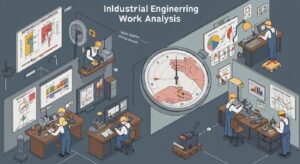

IEというとすぐインターネット・エクスプローラー?って思っていたのですが。
最近はちゃんとインダストリアルエンジニアリングって脳内変換されるのでまあ継続は力なんだろうなと実感。









