問題
Ⅲ-17 工程能力に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 工程能力は、工程の特性値の分布が正規分布とみなされるとき、一般に平均値±σで表される。
② 工程能力は、ヒストグラム、グラフ、管理図等によって図示することもある。
③ 工程能力は、安定した工程のもつ、特定の成果に対する統計的な工程変動を表したものである。
④ 工程能力は、一般に工程のアウトプットである品質特性を対象とする。
⑤ 工程能力指数は、特性の規定された公差を工程能力で除した値である。

解答
正解は 1 になります。
工程能力とは何か
工程能力とは、ある製造工程や仕事の流れがどれだけ安定して、望ましい品質を安定して維持できるかを示す指標です。これにより、製品やサービスのばらつきやムラを管理することができ、効率的な生産やクレームの削減に役立ちます。
工程能力を評価する際、「分布」「標準偏差(σ)」「管理図」などのキーワードが頻出です。例えば、製品の長さや重量のバラつきを分析して、どれくらい安定して規格内に収められるかを確認するときにも工程能力が使われます。
選択肢ごとの詳細解説
選択肢①
工程能力は、工程の特性値の分布が正規分布とみなされるとき、一般に平均値±σで表される。
詳細解説:
工程能力を数値で表す際、単純に「平均値±σ」で示すと、個々のばらつきしか分かりません。
実際には、工程能力は規定値に対し、どれだけ多くの製品が規格内にあるか(例えば±3σに何%収まるか)などでも評価されます。
平均±σでは分布の約68%しかカバーできず、工程能力の評価には不十分です。
工程能力は、例えば$$C_p$$や$$C_{pk}$$などの工程能力指数を使って、公差(規定範囲)との比較で評価することが一般的です。このため「平均±σで表される」は不適切です。
選択肢②
工程能力は、ヒストグラム、グラフ、管理図等によって図示することもある。
詳細解説:
実際の製品データや工程データは、ヒストグラム(度数分布表)や管理図(工程が安定しているかを示す時系列のグラフ)などによって可視化されます。
これによって、工程のバラつきや安定度がひと目で分かるため、工程能力の分析には必須の手法です。
選択肢③
工程能力は、安定した工程のもつ、特定の成果に対する統計的な工程変動を表したものである。
詳細解説:
工程能力は、工程が十分に統計的に管理され、安定した状態である場合(すなわち管理図でみて特別な変動がない状態)、その工程の通常の変動範囲を数字で表します。
不安定な工程では、工程能力を算出しても意味が薄いです。
安定した状態の変動こそ、工程能力の本質的な定義です。
選択肢④
工程能力は、一般に工程のアウトプットである品質特性を対象とする。
詳細解説:
工程能力を評価する際に注目するのは、「アウトプット=製品やサービスの品質特性」です。
例えば寸法、重さ、硬さ、強度などです。インプット(原材料の状態など)ではなく、得られる成果(アウトプット)が工程能力評価の中心となります。
選択肢⑤
工程能力指数は、特性の規定された公差を工程能力で除した値である。
詳細解説:
「工程能力指数(C_p)」は、製品の規格(公差)幅を工程のばらつき幅で割って求めます。
例えば製品Aの公差が±0.5mm、工程のばらつき幅が±0.2mmなら、$$C_p = \frac{0.5}{0.2} = 2.5$$となり、数値が高いほど優れた工程と言えます。
まとめ・重要ポイント
工程能力は、工程の安定性や品質管理、工程能力指数(C_p、Cpk)の算出といった専門的な分析手法で評価される。
また、工程能力の本質は「安定した工程におけるアウトプットのばらつき」を捉えることです。正規分布の平均値±σだけでは工程能力を網羅できません。
感想
工程能力もよく出ますね。
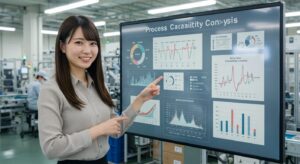
下の方のリンクにも並んでいると思います。
頻出問題、なのかな~と思います。
そのせいか、今日のはしっかりと正解でした。
6σとか辛い環境もあるんだから平均値程度じゃなかろう、と。









