問題
Ⅲ-7 連合作業分析に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 連合作業は、複数の人や機械が単独作業と協同作業を互いにもって、相互に作業のタイミングに拘束を受けながら協同して行う作業をいう。
② 連合作業は、生産現場でしか見られない作業である。
③ 連合作業分析では、人の手待ちを排除し、省人化を図ることができる。
④ 連合作業分析では、機械の停止時間を排除し、稼働率を上げることができる。
⑤ 連合作業分析では、人の作業名を「単独作業」、「連合作業」、「手待ち」に分類する。

解答
正解は 2 になります。
連合作業分析の概要
連合作業分析は、複数の作業者や機械が協力して作業を行う現場において、その作業の流れや効率を「見える化」し、ムダやロスを発見・改善するための分析手法です。
主に製造現場で使われるイメージがありますが、実際には事務作業や医療、工事現場など幅広い分野で活用されています。
分析では、作業を「単独作業」「連合作業」「手待ち(不稼働)」の3つに分類し、チャート(M-MチャートやManチャート)を作成して現状を把握します。
この手法により、作業者や機械のムダな待ち時間を減らし、生産性向上や省人化、設備稼働率の向上などが期待できます。
各選択肢の詳細解説
① 連合作業は、複数の人や機械が単独作業と協同作業を互いにもって、相互に作業のタイミングに拘束を受けながら協同して行う作業をいう。
この選択肢は正しい内容です。
連合作業とは、複数の人や機械がそれぞれ単独で作業する部分と、協力して行う部分を持ち、互いにタイミングを合わせながら進める作業形態を指します。
例えば、1人の作業者が機械の操作をしつつ、別の作業者が材料を準備するなど、作業の流れが連携しています。
② 連合作業は、生産現場でしか見られない作業である。
この選択肢が最も不適切です。
連合作業は生産現場だけでなく、事務作業や医療現場、工事現場、交通機関など、さまざまな分野で見られます。
たとえば、病院での手術チームの協力作業や、オフィスでの書類作成プロセスなども連合作業に該当します。
したがって、「生産現場だけ」というのは誤りです。
③ 連合作業分析では、人の手待ちを排除し、省人化を図ることができる。
この選択肢は正しいです。
連合作業分析の大きな目的の一つは、人の「手待ち」時間(作業ができずに待っている時間)を減らし、効率よく人員配置を行うことです。
これにより、必要な人員を削減し、省人化が実現できます。
④ 連合作業分析では、機械の停止時間を排除し、稼働率を上げることができる。
この選択肢も正しいです。
連合作業分析では、機械の停止時間(作業者が機械の動作を待っている間など)を減らすことも目的の一つです。
機械の稼働率を上げることで、生産効率が向上します。
⑤ 連合作業分析では、人の作業名を「単独作業」、「連合作業」、「手待ち」に分類する。
この選択肢は正しいです。
連合作業分析では、作業を「単独作業」「連合作業」「手待ち(不稼働)」の3つに分類します。
これにより、どこにムダやロスがあるのかを明確にし、改善策を立てやすくなります。
連合作業分析のイメージ図
| 作業者/機械 | 時間1 | 時間2 | 時間3 | 時間4 | 時間5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 作業者A | 単独 | 連合 | 手待ち | 連合 | 単独 |
| 機械 | 手待ち | 連合 | 単独 | 連合 | 手待ち |
このような表を作成し、どこに「手待ち」や「連合作業」があるかを可視化します。
まとめ:問題の要点
- 連合作業分析は、複数の人や機械の作業を「単独作業」「連合作業」「手待ち」に分類し、効率化を目指す手法。
- 連合作業は生産現場だけでなく、さまざまな業種・現場で見られる。
- 目的は、手待ちや機械の停止時間の削減、省人化や稼働率向上。
- 最も不適切な選択肢は「② 連合作業は、生産現場でしか見られない作業である」。
感想
今日もなんとか正解でした。
先日業務で少しやったんですよね、連合作業分析。
だから少し覚えていたというのもあります。
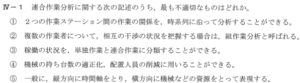
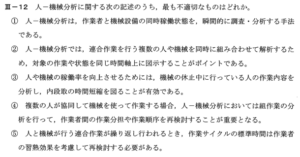

過去問でもよく出てきます。
ここもしっかり復習しますかね!!









