問題
Ⅲ-12 納期管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 注文件数に対する納期遅れ件数に基づく納期遅れの発生率を分析すれば、納期管理における納期遅れ時間を管理することができる。
② 全社的な納期管理の取組では、守れる納期の設定方法の確立、納期遵守の仕組みの構築、及び納期遅れが予想されるときのための納期遅れを挽回する仕組みの構築が必要となる。
③ 情報機器の発達により現在の情報をリアルタイムに見て統制活動ができるようになっているため、納期管理に必要な情報は何かという判断と、それらの情報を正確に得る方法を見出すことが重要である。
④ PERTによって作成されたプロジェクトの日程計画において、完了日が納期を満たしていても、クリティカルパス上の作業が予定より遅れた場合には納期遅れが生じる可能性がある。
⑤ 製造工程の負荷量に対し余力がマイナスとなる場合に、適切な余力管理が行われなければ、納期遅れの発生率は高くなる。

解答
正解は 1 になります。
納期管理の概要
納期管理は、受注した製品やサービスを決められた納期通りに納品・完成させるための管理活動です。
遅延が発生しないよう工程進捗を細かく把握し、問題があれば早めに対策を打つことが求められます。
企業活動において納期遵守は顧客満足や取引信頼性、コスト管理などに直結する重要な要素です。
近年は情報技術の発達とともに、リアルタイムでの状況把握や分析も高度化しています。
各選択肢の詳細解説
① 注文件数に対する納期遅れ件数に基づく納期遅れの発生率を分析すれば、納期管理における納期遅れ時間を管理することができる。
「発生率」は、たとえば100件の注文のうち5件が遅れた→納期遅れ「発生率」は5%という指標です。
しかしこれだけでは、どれだけ遅れたのか「時間的な深刻度」は把握できません。
納期遅れ「時間」の管理には、実際の遅延時間(例:3日遅れた、5時間遅延など)の集計が不可欠です。
遅れ件数の割合(発生率)だけを監視しても、「短期間の遅れ」と「大幅な遅れ」の違いを判別できないため、納期管理における遅れ時間の正確なマネジメントには不十分です。
この記述は納期遅れの「発生率」と「遅れ時間」の意味を混同しており、納期管理の観点から最も不適切です。
② 全社的な納期管理の取組では、守れる納期の設定方法の確立、納期遵守の仕組みの構築、及び納期遅れが予想されるときのための納期遅れを挽回する仕組みの構築が必要となる。
納期管理を全社で強化するには「守れる納期を最初から設定すること」「納期遵守の仕組み(工程把握や進捗監視など)を固めること」「万一遅延しそうな場合にどうリカバリーするか」というバックアップ体制の構築が基本とされます。
多くの製造業やサービス業が同様のマネジメントサイクルを採用しています。
したがって、この記述は妥当です。
③ 情報機器の発達により現在の情報をリアルタイムに見て統制活動ができるようになっているため、納期管理に必要な情報は何かという判断と、それらの情報を正確に得る方法を見出すことが重要である。
情報システムやIoT、MESなどの普及によって、現場の生産進捗や工程状況をリアルタイムに把握しやすくなっています。
ただし、どの情報が納期管理上重要かの見極めや、そのデータを正確に・タイムリーに収集する仕組みづくりが重要です。
これは現代の納期管理の基本的な課題認識であり、正しい内容です。
④ PERTによって作成されたプロジェクトの日程計画において、完了日が納期を満たしていても、クリティカルパス上の作業が予定より遅れた場合には納期遅れが生じる可能性がある。
PERT(Program Evaluation and Review Technique)は複数の作業が絡み合うプロジェクトの日程計画を可視化するための手法です。
特に「クリティカルパス」と呼ばれる一連の作業経路上で遅延が生じると、プロジェクト全体の納期が遅れるリスクがあります。
よって、この記述はプロジェクトマネジメントの重要なポイントを正しく示しています。
⑤ 製造工程の負荷量に対し余力がマイナスとなる場合に、適切な余力管理が行われなければ、納期遅れの発生率は高くなる。
「余力管理」とは、各工程での作業能力と仕事の負荷のバランスを管理する手法です。
負荷が能力を上回る=余力がマイナスの場合、遅延発生リスクが高くなります。
これを見越して適切な人員調整や計画変更、外注活用などを行い、遅延を未然に防ぐ必要があります。
この記述も正しいです。
まとめ
- 納期管理では件数の発生率分析だけでは遅延の大きさや深刻度を把握できず、遅延時間のマネジメントにはならないことに注意が必要。
- 全社的な納期管理の仕組み作り、リアルタイム情報の活用、日程計画(特にクリティカルパス管理)、生産負荷と能力バランスの把握は全て納期遅れを防ぐための基本動作である。
- 納期遅れの発生率と遅れ時間の意味を混同しないことが、納期管理実務で最も重要なポイント。
感想
おお、今日は納期管理ですか。
昨日に引き続き、これも毎日やってますよ!
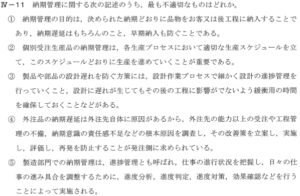
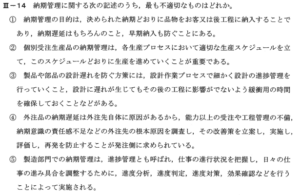
過去問にも登場しますが、ちょっと系統の違う問題ですね。
ちなみに今日はまんまと間違えました。
よくよく問題見たらああなるほど、って感じでした。残念!!









