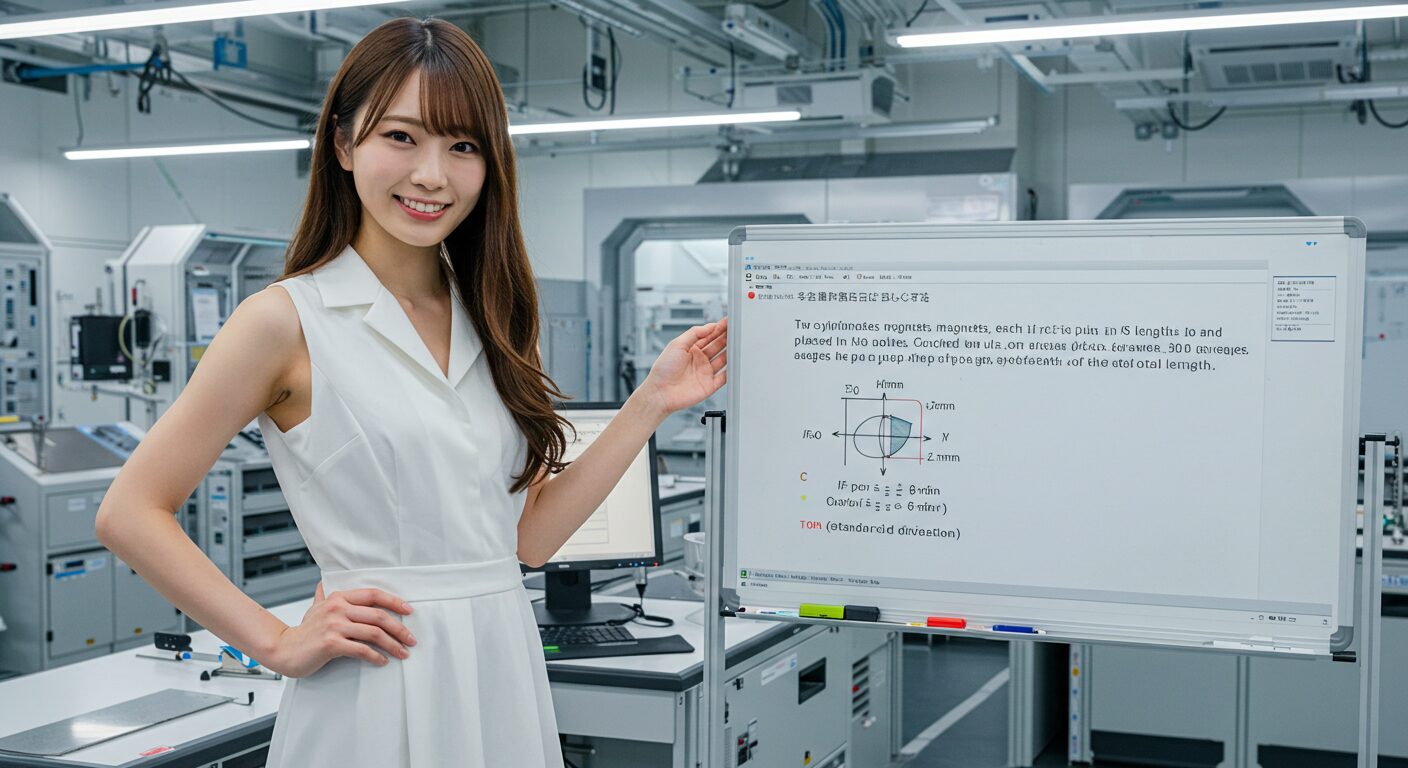問題
Ⅲ-17 長さが平均100mmで標準偏差が2mmの正規分布に従う直径8mm±0.2mmの2本の丸棒の磁石があり、その2本の棒磁石の両端はそれぞれN極とS極に同様に着磁されている。これら2本の棒磁石を摩擦のない幅10mmのV字型の溝に、互いに反発しあう最も近接させた状態で静止させて直線状に置いたとき、2本の棒磁石全体の長さの標準偏差として、最も適切な値はどれか。ただし、この反発状態における2本の棒磁石の間隔は、平均30mmで標準偏差が2mmの正規分布に従うものとする。
① 4㎜
② 6㎜
③ √6㎜
④ 2√3㎜
⑤ 8㎜
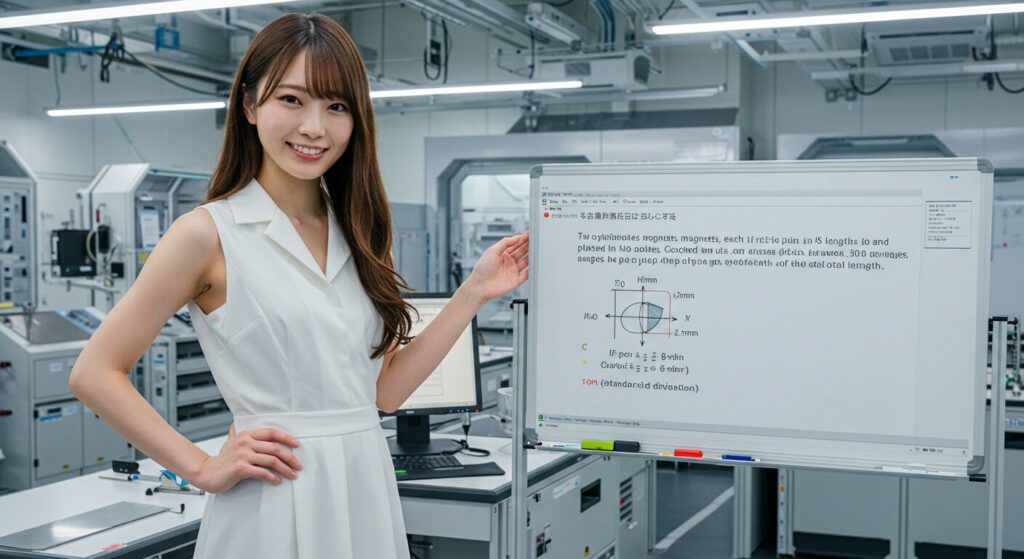
解答
正解は 4 になります。
概要
この問題では、「2本の丸棒磁石」と「それらの間隔」に関する標準偏差の計算が問われています。
各丸棒磁石の長さは正規分布に従い、間隔もまた正規分布に従います。
最終的に求めるのは、2本の棒磁石全体(=1本目の長さ+2本目の長さ+間隔)の「標準偏差」です。
問題設定の詳細理解
- 丸棒磁石(2本)の長さ:それぞれ平均100mm、標準偏差2mmの正規分布
- 棒磁石の間隔:平均30mm、標準偏差2mmの正規分布
- 全体の長さ:「1本目の長さ+2本目の長さ+間隔」
- ※いずれも独立した正規分布に従うと考えてよい
標準偏差のポイント
- 複数の独立した変数の和の標準偏差
独立した変数 $$X$$, $$Y$$, $$Z$$ の標準偏差がそれぞれ $$\sigma_X, \sigma_Y, \sigma_Z$$ だとした場合、
合計 $$S = X + Y + Z$$ の分散は、
$$\mathrm{Var}(S) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + \mathrm{Var}(Z)$$
標準偏差は
$$\sqrt{\sigma_X^2 + \sigma_Y^2 + \sigma_Z^2}$$
となります。 - 今回の適用
各丸棒磁石の標準偏差は2mm、間隔の標準偏差も2mmなので、計算は以下の通りです。
各選択肢の詳細解説
① 4mm
- 計算式:
2本の棒(標準偏差2mmずつ)+間隔(2mm)
$$\sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{12} ≒ 3.464mm$$ - この値より大きいので、4mmは過大評価しています。
② 6mm
- 計算式:
$$\sqrt{6^2} = 6mm$$ - 6mmという数値は、「誤って単純合計(2+2+2)」をした場合の数値です。
- 「標準偏差は単純加算できない」という点が理解できていない例です。
③ √6mm
- 計算式:
$$\sqrt{6} ≒ 2.45mm$$ - これは、各標準偏差「2mmを3つではなく、それぞれ1本ずつ1mmと仮定」した場合か、あるいは間違った式変形結果です。
- 実際の分散が合計「6」で標準偏差が√6になるという解釈ですが、今回はそれぞれ2mmなので不適。
④ 2√3mm (正解)
- 計算式:
3つの標準偏差がすべて2mm
$$\sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 4 + 4} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}mm$$ - これが理論的に正しく、該当する選択肢です。
⑤ 8mm
- 計算式:
これも「加算ミス」あるいは「最大値」のような過大評価です。 - 標準偏差は和ではなく分散の和の平方根という性質です。
まとめ
今回の問題の重要ポイントは、独立した変数の合成標準偏差の扱いです。
複数の要素(長さや間隔)が独立してばらつきを持つ場合、それら全体の標準偏差は「単純な合計」ではなく、各分散(標準偏差の二乗)の和をとり、その平方根をとるのがポイントです。
公式としては$$\mathrm{合成標準偏差}=\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2+\sigma_3^2}$$
となります。
感想
今日は正解でした!
開発ものの設計をやっていたとき標準偏差にはお世話になっていましたからねえ。
片公差よりも公差が±で表せるよういろいろ工夫もしていました。
でもこの試験で標準偏差自体にフォーカスが当たるのは初だと思います。

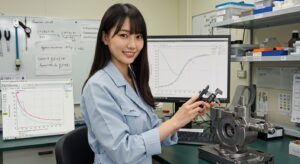
過去問もこれくらいですからね。
今後はこのての問題、増えるのだろうか。