問題
III-10 レイアウト計画に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① P-Q分析は、需要予測や市場調査によって得られたデータに基づいて、製品の種類Pをその数量Qの大きな順に並べてグラフを作成し、両者の関係から製品の生産形態を分類し、レイアウト計画に活用する手法である。
② R.Mutherによる体系的レイアウト計画(SLP)は、立地選定、基本レイアウト、詳細レイアウト、設置の4段階からなっている。
③ 工場レイアウトにおける運搬の検討では、運搬対象物の移動のしやすさ、すなわち運びやすさや動かしやすさの指標である運搬活性示数を高める考え方が重要である。
④ 工場内に配置する種々の部門間の定性的な関係は、近接性の評価とその理由を示す相互関係図表にまとめることができる。
⑤ 生産対象となる品種や量などの生産条件について短期的な変化が生じ、これに対応するため部分的にせよ設備や作業場所のレイアウトを変更することは避けなければならない。

解答
正解は 5 になります。
問題概要
この問題は「レイアウト計画」に関する知識を問うものです。
レイアウト計画とは、工場や施設内での設備や作業場所の配置を計画するプロセスのことを指します。
効率的なレイアウトは、生産性向上やコスト削減に大きく貢献します。
各選択肢の解説
① P-Q分析について
記述内容:
「P-Q分析は、需要予測や市場調査によって得られたデータに基づいて、製品の種類Pをその数量Qの大きな順に並べてグラフを作成し、両者の関係から製品の生産形態を分類し、レイアウト計画に活用する手法である。」
解説:
P-Q分析とは、生産管理や在庫管理でよく使われる手法です。「P」は製品(Product)、「Q」は数量(Quantity)を表します。この分析では、製品を数量順に並べたグラフを作成し、それによって製品の重要度や生産形態(大量生産向きか、小ロット生産向きかなど)を分類します。これにより、効率的なレイアウト計画が可能になります。
評価:
この記述は正しいです。P-Q分析はレイアウト計画において有用な手法として広く認識されています。
② SLP(体系的レイアウト計画)について
記述内容:
「R.Mutherによる体系的レイアウト計画(SLP)は、立地選定、基本レイアウト、詳細レイアウト、設置の4段階からなっている。」
解説:
SLP(Systematic Layout Planning)は、工場や施設のレイアウト設計を体系的に進めるための手法です。R. Mutherが提唱したこの手法は、以下のようなプロセスで進められます:
- 立地選定(Site Selection): 工場全体の場所を決定。
- 基本レイアウト(General Layout): 大まかな配置案を作成。
- 詳細レイアウト(Detailed Layout): 各設備や作業場所を具体的に配置。
- 設置(Installation): 実際に設備を設置。
ただし、この記述には誤りがあります。本来SLPでは、「立地選定」は含まれておらず、「関係図表」「スペース配分」「改良案作成」などが主要ステップです。
評価:
この記述は不正確です。SLPには「立地選定」が含まれないため注意が必要です。
SLP自体は本来、「基本レイアウト」と「詳細レイアウト」に特化した手法であり、「立地選定」はその範囲外とするのが正確です。しかし、一部では「立地選定」を含む広義の解釈が存在するため、文脈によって異なる理解があることを認識しておくべきです。
③ 運搬活性示数について
記述内容:
「工場レイアウトにおける運搬の検討では、運搬対象物の移動のしやすさ、すなわち運びやすさや動かしやすさの指標である運搬活性示数を高める考え方が重要である。」
解説:
運搬活性示数とは、工場内で物資や製品を効率よく移動させるための指標です。この値が高いほど運搬効率が良いとされます。例えば、物資が短い距離で移動できる配置や、自動化された運搬システムなどが考えられます。
評価:
この記述は正しいです。工場レイアウトでは運搬効率が重要視され、そのため運搬活性示数も重要な指標となります。
④ 部門間関係と相互関係図表について
記述内容:
「工場内に配置する種々の部門間の定性的な関係は、近接性の評価とその理由を示す相互関係図表にまとめることができる。」
解説:
相互関係図表(Relation Diagram)は、各部門間の関係性を視覚的に整理するためのツールです。この図表では、「どの部門がどれだけ近接しているべきか」を評価し、その理由も併せて記載します。例えば、「部門Aと部門Bは材料供給で密接な関係があるので隣接させるべき」といった情報が含まれます。
評価:
この記述も正しいです。相互関係図表はSLPなどでよく使用されます。
⑤ 生産条件変化への対応について
記述内容:
「生産対象となる品種や量などの生産条件について短期的な変化が生じ、これに対応するため部分的にせよ設備や作業場所のレイアウトを変更することは避けなければならない。」
解説:
この記述には誤りがあります。現代の製造業では、生産条件(品種・量など)の変化に柔軟に対応できるような「柔軟性」を持つことが求められています。そのため、生産条件が変化した場合には必要に応じて設備や作業場所を再配置することも重要です。このような柔軟性は競争力強化につながります。
評価:
この記述は不適切です。生産条件変化への対応力は非常に重要であり、それを避けるべきという考え方は現代的ではありません。
まとめ
問題要点
- レイアウト計画では、生産性向上や効率化を目指して適切な配置方法・手法を学ぶことが重要。
- 各選択肢について正誤判断する際には、それぞれの手法・概念について正確な知識が求められる。
- 正解は⑤。不適切なのは、生産条件変化への対応力を否定している点。
感想
引っかけ問題、なのだろうか・・・。
2でも正解でいいような気もしますが、圧倒的に5が不正解なので、ということなんでしょうかね。
ここで運搬活性示数、にまたもや躓きました。
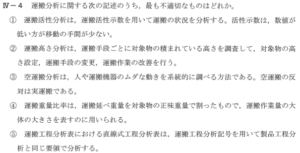
活性示数は、数値が高い方が移動の手間が少ない。でしたね!
危ない危ない。
床のバラ置きが低い!いい加減覚えよう。
レイアウト変更、大好きです。
ワタクシの場合はも自分の部屋の模様替え、というレベルですが(笑)
いずれにしても柔軟性大事ですね!









